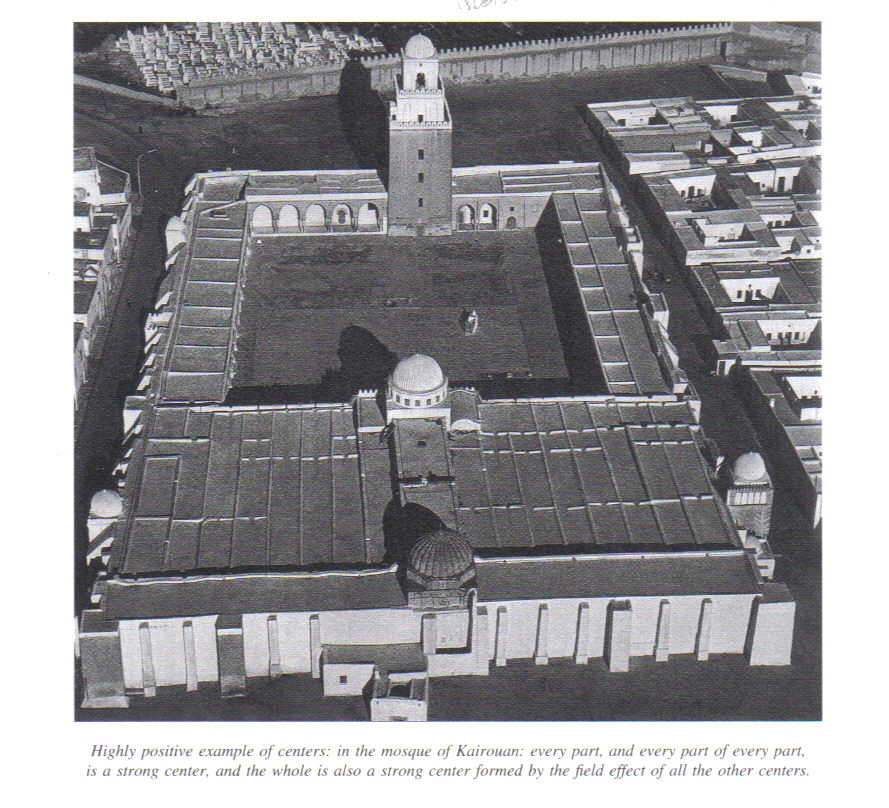
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�@�@�@
�@�@�@�@�@�����n�b�s�[�ɂȂ���ދ�Ԃ�����܂��傤�I�I��
�@�@�@ �@
�@�@�@�@�@�E-�E-�E�@�P�T�̊w�I�����\�������S���\�@�E-�E-�E
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�Ԋ��̒��A���j���̏t�����̓V�C���v���o���A
�O���l���̓��ɁA���̊Ԃɂ��G�߂��ڂ�ς���Ă��邱�̍��ł��B
����ɂ��Ă��A���N�̍��͑f���炵���A
�Ԑ�������̐��̂��̂Ƃ͎v���Ȃ����ł����ˁB(*^o^*)�@
�F�l�A�����C�ł����B
�����A���w�ǂ��肪�Ƃ��������܂��B(*^o^*)�@
���́A���ׂɈ��������ԕ��ǂɂȂ�A
�ǂ���ׂ̈̕@���������܂��ŁA�ǂ���̖�����߂����̂������A
�g�̂����R�ƈ�́A�g�̓������ЂƂ̑S�̂Ɩ��ɔ[��������X�ł����B
���āA�O��́A�u�����Ă���\���v��
�u�����Ă���v���Z�X�v���琶�܂�Ă���ƁA
�����Ɣ�����Ă���u�P�T�̊w�I�����v�ɂ��Đi�ߎn�߁A
�uLEVEL�@OF�@SCHELE�F�傫���̒i�K���v�����グ�܂����B
����́A�uSTRONG CENTER�F�������S���v�ɂ��āA���Ă����܂��傤�B���(^o^)���
(The Nature of Order �U�@p.151�`p.164)
����������������������������������������������������������
�uSTRONG CENTER�F�������S���v
C�E�A���O�U���_�[�́A�u15�̐����̂��ꂼ����ςčs���ƁA
���̎��̕ʂ̐����ɋC�Â��Ă����Ƃ����X��������܂����B
�Ⴆ�A�u�傫���̒i�K���v���ςĂ���ƁA
�e�X�̑傫���̃��x���ŁA
�l�X�ȃZ���^�[�ɁA�S�̐����A�����ڂ���Ƃ������̂����A
�u�������S���v�ɋC���t���n�߂�̂ł��B�v�Ǝn�߂Ă��܂��B
�@
�@�����ƑO�ɁA���S���Ƃ������Ƃ��A
�S�̐��ނ̂Ɍ��ƂȂ�v�f�ł���Ƃ��āA
����ʓI�Ȓ��S���̖����ɂ��Ď��グ�����Ƃ�����܂����B
�����ł́A�P�T�̊w�I�����̂ЂƂƂ��āA
�S�̂̊e�v�f�Ƃ��đ��݂��Ă���Z���^�[���A
�X�ɋ��߂Ă���Ƃ������S���ɂ��Ăł��B(^_-)��
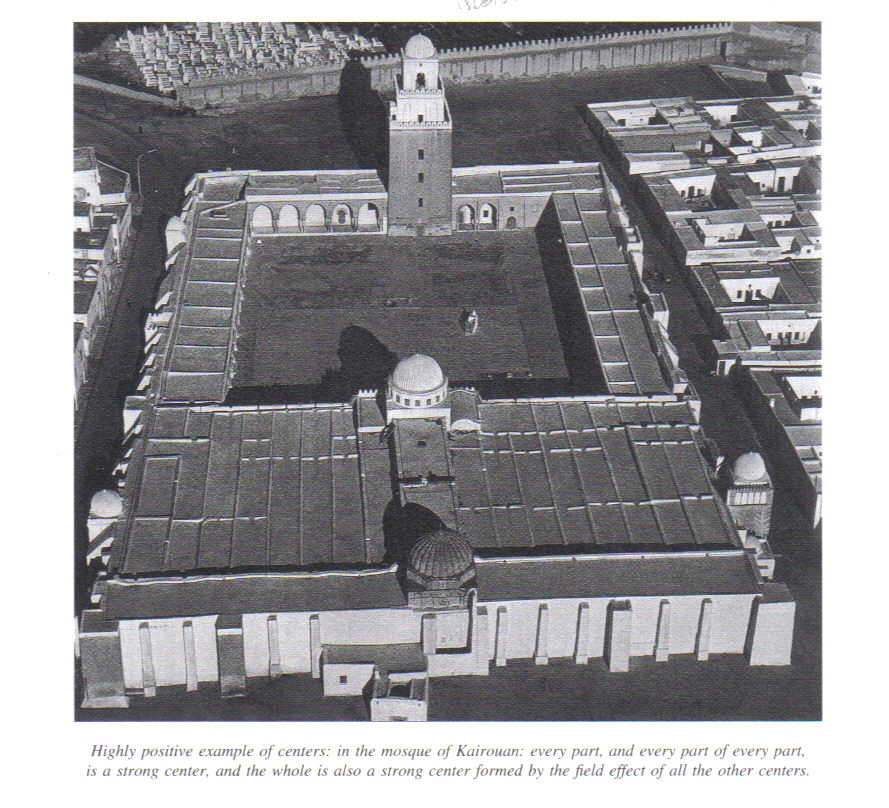
�A���O�U���_�[�����͑����Ă��܂��B
�u�ۗ�������Ƃ��āA
�݂��ɃZ���^�[�����ߍ����Ă���̂����ĉ�����J�C���̃��X�N�ł��B
�����ŁA���B�́A�����݂̌��ɋ��ߍ����Ă���Z���^�[��ڂɂ��邱�Ƃ��o���܂��B
�傫�Ȓ���A��h�[��(�V�W)�A���h�[���A�X�̏e��t���̋��ǁA�i�X�A������A
�X�̃A�[�`�A�����̕����ł������A���ꂼ��̃Z���^�[���݂��ɋ��ߍ����Ă��܂��B
�X�ɁA���ꂼ��̕����͑Ώ̐�������Ă��܂��B
���ꂪ�A���ʂƂ��āA�������S���������N�����Ă���̂ł��B
���ꂼ��̊e�Z���^�[�́A���̎��͂Ƀt�B�[���h�A����`������̂ł��B
�����āA����́A�����̕����I�Ώ̐����Ċg�����Ă���悤�ł��B
���Ƃ��A�J�C���̃h�[���̃p���[�́A
�R�̃h�[���̑O�i���Ă����悤�ȘA�Ȃ�ɂ���Ĉ����N������Ă���̂ł��B
���ꂼ�ꂪ�A��荂���ƁA���_�Ƃ��Ă̎�h�[���ɓ���悤�ɂƓ����Ă��܂��B
�S�Ă̍\���́A���̎�h�[���̂��߂Ɍ��Ă�ꂽ�̂ł��B(^_-)��
���ۂɁA���B�́A�Z���^�[�A���S�Ƃ��Ă̂��̃h�[����m�o���܂��B
�B�A�h�[���̌`����݂̂ł͂Ȃ��A
���̔z�u�A�S�̂Ƃ��ẮA�����I�����̒��ŁA
���̃h�[�������w�I�����ɂ���ĂȂ̂ł��B(^_-)��
���ɁA��茀�I�ɗ������邱�Ƃ��o�����ł��B
�P�W���I�̃A�i�g���A���E�J�[�y�b�g�̐ؕЂ����Ă݂܂��傤�B
����́A���S���̓������A�X�g���[�g�ɋ����ׂ��x�����Ŕ����Ă��܂��B
�قƂ�ǑS�Ă̗ǂ��J�[�y�b�g�́A�����̋������S��������Ă��܂��B
�w�I�Ȓ��S���ł���K�v�͂Ȃ��A
�������A���ӂ��������S���ŁA�œ_�Ƃ��Ă̒��S���ł��B(^_-)��
�������A���̒��S/�Z���^�[���A�P�ɒ����ɍ݂邾���̂��̂Ȃ�A
�M���������ɍ����Ĕ킳�������ɏ����Ă��܂��܂��̂ŁA
���̃p���[�͂��Ȃ�ア���̂ƌ����܂��B
�������S���Ƃ��Č����ׂɂ́A
�J�[�y�b�g�S�̂��A���̒������x���Ď��͂��͂��w���\�����A
�N�����A�J�[�y�b�g�ɋ߂Â��ƁA���̒��S�ɋC���t���āA����ɖڂ𗯂߂āA
�������痣��Ė��߂��ė����Ƃ��ɁA�����悤�ɌJ��Ԃ���Ƃ����悤�Ȋ������A
�����Ȃ��N����̂ł��B(^_-)��
�|�^���L��̗���A���̋������S�������Ď��܂��B
�A�[�P�[�h�A���A�����A�����ăf�B�e�B�[��/�ڍ��c�c�c.,�A
���ꂼ�ꂪ�A�S�̂�ʂ��Ẵt�B�[���h/��̌��ʂɍv�����Ă��܂�(^_-)���B
����ŁA���㌚�z�ł́A���̃Z���^�[�̃q�G�����L�[(�K�w��)��n��̂́A
�x�X����Ȃ��Ă���悤�ł��B
�Ȃ��Ȃ�A���ۏ�A�����炭�����Z���^�[�ɂ���̂�������Ȃ�����ł��B
�����̉Ƒ��̓T�^�I�ȃv����/�Ԏ��ŁA�������S�ɂȂ�ł��傤���B
�i���Ƃ̈͘F����A�{���̏��@�̏��̊Ԃɔ�ׂāA���ЂƂA���Ă��������܂��B�j
�����ɏZ�ސl�ԊW�Ɠ����悤�ɁA�s����ł͂Ȃ��ł��傤���B
����̉Ƒ����̂��A���S�������Ă���Ƃ������Ƃf���Ă���悤�ł��B
���B���A��������������@��m���Ă����Ƃ��Ă��A
���̌��z�̒��ŁA���x���̘A������������ɏ[���d�v�ȋ@�\�́A���Ȃ̂��A
�L�b�`�����A����Ƃ������o�@�\����������r���O���[�����A�m���ł͂Ȃ��̂ł��B
�����̋@�\�́A�d�v�ł����Ă��A���܂�Ɋ���I�ɒ����I�ŁA
�͋����w�I�Ȓ��S�����x���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł��B
�ȑO�A�͋������S�ƂȂ��Ă����̂́A�g�F�A��Q���̃x�b�g�A�H���c.�A
�����́A���͂�A�����Ă̗͂������Ƃ������A
�Ȃ��Ȃ�l�Ƃ��āA�Ƒ��Ƃ��Ă��A
���B�̒��ɂ́A���S�����o���Ă��Ȃ��̂ł�����B
����I�Ƒ��̌˘f�����A�����̏Z��̒��S���̌��@�Ƃ��āA����Ă���̂ł��B
�������Ȃ���A�Z���薾�炩�Ȓ��S�A
�G�l���M�[���W�܂��Ƃ��Ă̒��S�������č\�����ꂽ���A
�Z��A�����Ɉꏏ�ɏZ�ސl�X�̐����ɂ����Ē��S�������Ă����̂ɁA
���e���͂̂�����̂ƂȂ��āA�܂��N���������Ƃ��Ȃ��͂���������̂ł��B
�Ⴆ�A�������S���̊T�O�𖾂炩�ɂ���ׂɁA
�t�����N�E���C�h�E���C�g�̏Z��̂ЂƂ����Ă݂܂��傤�B
����́A�ЂƂ̒��S����n�������̌��ʂɂ��āA���B�Ɋw���Ă���܂��B
��̌��ʂƁu���́v�Z���^�[�̗͂́A
����ɓ���܂œ������̋߂��̊���̃Z���^�[�̘A�Ȃ�ɂ���āA
�n������Ă��܂��B
�ǂ���Ƃ��āA�@���I���z�̐g�L������܂����A
�ЂƂ̏I�[�ւƒB���钌�Ԃ̘A���́A����炪�S�ē������ϓ��ł�������A
���̃N���C�}�b�N�X�ւƓ����Ȃ���A�ǂ�ǂ܂��Ă��������Ȃ̂ł��B
����������������������������������������������������������
��ʓI�ɁA������v�ȍ\���ƁA������x���鑼�̍\��������܂��B
�S�̐����ЂƂ̍ő�̍\��������̂ł��B
���ɁA���̏d�v���A�܂��͒��S���́A�ꌩ���ĉ�����悤�ȁA
�����ȕ����A�ڍׂɂ���đn���Ă��܂��B
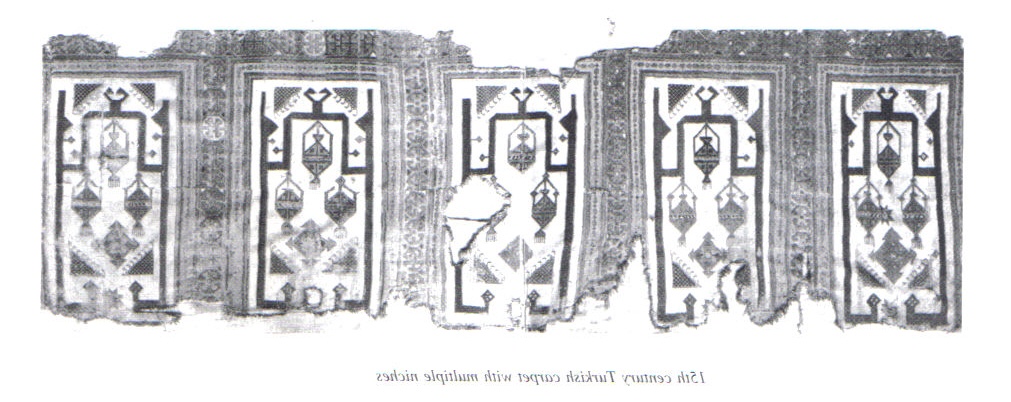
�Ⴆ�A�F���p�J�[�y�b�g�̃A�[�`�ɒ݂邳��Ă��郉���v�́A
�m���Ȗ����������Ă��܂��B�ڂ𗯂܂点�A���S��n��Ƃ��������ł��B
�������Ȃ���A����́A�ЂƂ̓_�ł́A�[���ł͂Ȃ��̂ł��B
����́A���ꎩ�̂ɂ����ăZ���^�[���`������\���ł��邱�Ƃ��K�v������ł��B
�����炭�A�Œ���A�ЂƂ̑傫�ȓ_�ł��邱�Ƃ��K�v�ŁA
���̉��ɂ�菬���߂�3�̓_���Ă��邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂ł��B
�X�ɁA����́A�㉺�t���܂ɂ��Ă݂邱�Ƃ��o���āA
�����v�łȂ��Ƃ��A�ǂ̂悤�ȃf�U�C���ł��ǂ��āA
�ЂƂ̋������S�����߂�ɏ[���ȍ\���������Ƃ��o����̂ł��B(^_-)��
5�̃j�b�`�A�ǂ̌E��(�ǂ���)�����A���G�Ő������ꂽ�J�[�y�b�g�̗�ł����A
�����v�́A���̃j�b�`���������S�Ƃ���̂ɁA����Ȗ�����S���Ă��܂��B
�j�b�`�̃Z���^�[���A�����v�ɂ���Č��ʓI�ɑn������Ă���ɂ�������炸�A
�Z���^�[�ł���̂́A�����v���ꎩ�̂ł͂Ȃ��̂ł��B
�����v�́A�P�ɋ�Ԃ�����t���āA
���傫�ȋ�Ԃɂ������̌��ʂ��N�����̂ɁA�𗧂��Ă���̂ł��B
�Z���^�[�́A���̗̈�𓌕��ɕ����t���āA
5�{��10�{�������v�����̂����A�傫�Ȓ��S�ƂȂ��Ă���̂ł��B
�����āA���ꂪ�A���̃J�[�y�b�g�ɐ[�����n�����Ă���̂ł��B
�����v�́A�����A�e�X�̃j�b�`�̐c�Ɍ������āA
�i��ł����悤�ȓ����̊��o��n���Ă��鑽���̍\���̂ЂƂł��B
����́A�������S����n������̂Ɉꏏ�ɓ����A
�����̈قȂ������S�S�Ă̌��ʂ���������āA��[�����[�ɋy�ԑS�̂Ȃ̂ł��B
�ǂ����āA�ЂƂ̃����v�����A�ЂƂ̓_���ア���Ƃ������R�́A
�����v���ꎩ�̂��A�������̑O�i����Z���^�[�̂ЂƂł���A
�����̂ЂƂ̃Z���^�[�ł͂Ȃ�����ł��B
�����āA���̂������̃Z���^�[�̑O�i�́A
���̂ЂƂ̏�ŁA�ЂƂ̓_���o��������A
��苭���t�B�[���h/����\�����邱�Ƃ��o����̂ł��B(^_-)��

�O��́uLEVEL OF SCHELE�F�傫���̒i�K���v�Ɠ����悤�ɁA
�uSTRONG CENTER�F�������S���v�̊T�O�́A�J��Ԃ��N����̂ł��B(^_-)��
�ʂɉ����A�ЂƂ̗��h�ȃZ���^�[������ƌ����Ă���̂ł͂Ȃ��āA
���Ȃ�l�X�ȃX�P�[���ŁA���B���Z���^�[�̑��݂������邱�Ƃ��o���āA
�قȂ����i�K�ł��̂������̈قȂ����Z���^�[�̑��l����
�����邱�Ƃ��o����̂ł��B(^_-)��
�����āA���ꂪ�A���B�������t����̂ł��B
�����̏ꍇ�A�x�ޏꏊ�Ƃ��A�����Ƃ��A
�ł��d�v�ȏꏊ�Ƃ�������̎�v�ȃZ���^�[���A
�S�̑g�D�̃Z���^�[�ł���̂ł����A
���̏ꍇ�ł́A�������������ނ悤�Ȃ��̂ł����A�ʐ^�̎��̂��M�̂悤�ɁA
��̃Z���^�[������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��ŁA
�g�����鏬���ȃZ���^�[�̘A���Ƃ��Ă���̂ł��B
����ł��A���̏����ȃZ���^�[���悭�ς�ƁA
�l�X�ȓ_�ő��̃Z���^�[����苭�߂Ă���ƔF�߂���̂ł��B
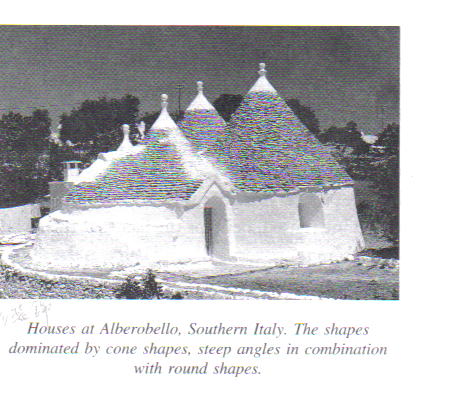
�A���x���x���̃g�������ɂ����ẮA
���ꂼ��̉����̒��_���A
�P�ɏ����ȃR�u�̂悤�Ȋۂ��o������ɂ���đn���Ă���̂ł͂Ȃ��A
�����S�̂��A���_�Ɍ������ďœ_���߂Č`����Ă���Ƃ��������ɂ���āA
���_�����F�œh���Ă���Ƃ��������ɂ���āA
�����Z���^�[�ƂȂ��Ă���̂ł��B
���ꂪ�A�Z���^�[�̊j�Ƃ��āA
���ɂ���ɒB����Ƃ����悤�Ȃ����ŁA�n���Ă���̂ł��B
�b���̃h�A�����́A�b���̏㉺�̂Q���̔ɂ���āA
�X�N�����[�Ńh�A�ɌŒ肳��Ă��܂����A
���̂Q���̃v���[�g�ɂ���āA�ЂƂ̃Z���^�[�Ƃ��Ă��̋����Ă��܂��B
��̃g���R�̎M�̎��́A�����Z���^�[�ƂȂ��Ă��܂����A
�Ȃ��Ȃ�A�����A�����ƌJ��Ԃ����~�`�̕��Ƃ���A
�˂��o�Ă���悤�Ȃ����ɂ���āA
���ׂČ���҂̒��ӂ����ɏW�������Ă���̂ł��B

�}�̒ʂ�s��`�ȃT���}���R�L��ɂ����ẮA
�S�Ă̏œ_�́A����������̓_�Ɍ������܂��B
����́A���Ӑ[���A��̌��ʂ�n��o�����߂ɏœ_���߂��Ă��邩��ł��B�v
����������������������������������������������������������
���āA���B�ɓ���݂̂�������݂Ă݂܂��傤�B
�g�߂ȂƂ���ɍ݂����A�n��Љ�̒��ł̒���̐X�A
����̐X�̒��̋����A�����̒��ŁA�����Ȃǂ̌��E����_�Ђɓ���܂ł̑S�āA
�����ĎЁA�Ђ̉����ނ������A���̋������S���̍\�����A
���A�l�X�ȗ��R�̌��A���J����Ő����A�ԗ���ʂ݂̂��l�������s�s�v�悩����A
�j�����܂����B
���̌��ʁA�Ђł����}���V�����̐A�����݂̈ꕔ�ɒu���̂悤�ɐݒu����Ă�����A
�ݔ����j�b�g�ƈꏏ�̉���ɒǂ�����Ă����肵�܂��B
���ɁA���S������������l�̐��_�\�����̂��̂ŁA
�c���������\���́A�����ɂ���O�����E�ɂ���Ƃ��A
�Љ�I�r�p��a���������Ղ���ԂȂ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
����A�j�Ƒ���R����Ƒ����W���Ƒ����Ƃ��ꂽ����ł́A
���w�Z���n��̒��S�ł����B
�Ƒ������l�����Ă��鍡���ł́A
���ꏊ�Ƃ������ƂŁA
�ً}�ЊQ�����v���Ə��w�Z���v�����ׂ�s�s���Z�҂������Ă���ł��傤�B
�q���̂��鐢�тɂƂ��ẮA������ۈ牀�⏬�w�Z�A
�d�ԒʋΎ҂ɂƂ��ẮA�w���ӁA�w�r������`���Ƃ�E����ӂł�������A
���N���ɂƂ��ẮA�n���ق�f�C�P�A�Z���^�[�ł������肷��ł��傤�B
���ꂩ��A�s�s�Ő[�ċz�ł���M�d�ȏꏊ�Ƃ��āA
�_����ʎ�����G�ؗт�����ȂǑ傫�ȉ�Ƃ��Ă̗Βn���Z���^�[�ɂȂ�����n�b�s�[�I�I
�ʊw�H�S�̂��������S���Ƃ��Ĉʒu�t����ꂽ��n�b�s�[�_(^o^)�^
����������������������������������������������������������
���A��ϔY��ł���̂��A���̎q�����ʂ��n�߂����w�Z�̒ʊw�H�ł��B
�n��ً̋}���ꏊ�ɂȂ��Ă����܂����A
���̒n��̒��S�Ƃ������ׂ����w�Z�ɓ���܂ł̒��S�����A
���ۂ̂Ƃ���A�S���Ȃ��̂ł��B�R(`�D�L)�m
�ʊw�H�Ƃ����Ŕ��d�M���ɕt���Ă���݂̂ŁA
�������K�[�h���[�����Ȃ������݂̂̓��H���ʊw�H�ƂȂ��Ă���̂ł��B
���̂R�O���ʂ́A�ԗ��ʍs�~�߂ɂȂ��Ă��Ă��A
�A��ɂ́A���ꂷ�������܂���B�R(`�D�L)�m
����ʍs�ɂ��Ȃ炸�A�Q�䂪����Ⴄ�ۂ́A�q�����ׂ����悤�ɂȂ�܂��B
���܂��ɑ�^�ԗ��̋K�����Ȃ��A
�������H�Ŋp�̑����Z��n��ŁA
��}�ւ���z���̑�^�ԗ������ɃX���X���ɋȂ����Ă���̂ł��B
���Ɏԗ��������ԂŁA�������ׂ��Œ�Ԃ����R�ŁA
�q���Ɍ�ʋK������邱�Ƃ��������āA
��l�͎�炸�Ƃ��A�ی��A���K�I�����ōς܂���Ă��܂��ԗD��Љ�ł��B
��Ⴢ��Ă��Ȃ����S�Ȑ_�o�̉^�]�҂ɂƂ��Ă��A���낵���ł��B
���́A�����^�]�҂ł��B
�a�̍s��̂悤�Ȓʊw�H�ł��������̋��낵���Ȃ̂ł��B�R(`�D�L)�m
�����班�q����A�q��Ďx���Ɨl�X�ȑ������Ă��A
����y�ȑ�����Ă���Ƃ����|�[�Y�ɉ߂��Ȃ��Ɗ����Ă��܂��ł��B
�q�������̂悤�Ȓʊw�H�⎙���قƂ��������X�y�[�X�ɉ������߂āA
�q���̏K����A�S�g�Ƃ��Ɍ��N�ɐ�������ߒ��̎q���̎��R��D���Ă���̂ł��B�R(`�D�L)�m
��ʋK�������Ȃ��q����A�ƒ��w�Z�̐ӔC�Ɖ����t�������̂ł͂Ȃ��A
�l�Ԃ̐���������A�Z���Ƃ��ēs�s���C�����Ă����̂��A
���I���N�A���S�Ȋ������߂��A�{���ɖ��邢�Љ��z���Ă������ƂɂȂ�̂ł��B(^_-)��
�䂪�A���ۑS�̌v��̂Ȃ��A
�ً}�ԗ��ʍs��G�ɂǂ��ɂł��Ԃ�ʂ��s�s�v��̖��ł��B�R(`�D�L)�m
�X�O�N�㏉�߂ɁA���ݏȂ̖����̓s�s�Z��Ƃ���������ŁA
���v���n�u��Ђ�}���V�����Ǝ҂��ꓯ�ɏW�܂�����c���A
�u�j���[���[�N�̃n�C�N���X�̎q���悤�ɁA
�q������l�̉^�]���鎩���ԂŒʊw����Ηǂ��v�ƁA
�^�ʖڂȈӌ��Ƃ��ďo�Ă����̂��A���̈ӎ��A���ꂪ�����ƂȂ�̂��ƁA
�킪���������܂ŕa��ł���̂��ƁA
�߂܂�������قǃK�[���ƏՌ��ł����B
����������������������������������������������������������
�ً}���̔��H�Ƃ��Ȃ�ʊw�H�ł�����A
�ʊw�H�����ł��d���݂��A���w�Z�Ɍ������ĉ���������i�߂�̂��K�{�ł��B
���ɁA�O�Ȃǂ̊������H������ɒʂ��O�ɁA�}���Ȃ̂ł��B
�ǂ����Ă��A�X�y�[�X�����Ȃ��ꍇ�́A
�d���̂Ȃ��q���̎��]�Ԃ��ʂ��ܓ���ݒu������ŁA
�ԗ��K�������ʍs�ɂ�����A�ʊw�H���Z���^�[�Ƃ��āA
���H�Ԃ̍čl���K�v�Ƃ���Ă���̂ł��B(^_-)��
��z�ւ̃g���b�N���A���̂悤�Ȋp�������������H�̏Z��n��ł́A
���^�Ԃɕς���ׂ��Ȃ̂ł��B�f�p�[�g�̏W�z���̂悤�ɉ\�Ȃ͂��ł��B
�}���ꍇ�́A�������珬�^�Ԃ�o�C�N�ւŎ�z����Ƃ����悤�ɁB
���w�Z���n��R�~���j�e�B�̕����{�݂ƂȂ��Ă��A
�n��̍���҂����S���ĂԂ�Ԃ��������S�ȉ����������ł�����n�b�s�[�I�I
����������������������������������������������������������
�����ŋ��k�ł����A����S���U���̉䂪�q�̓��w���̓��ɁA
���̑O�̎n�Ǝ����I�����A�R�N���ɐi����������̏��w�����A
��ʎ��̎��ő��E����܂����B
���܂�ɔ߂����g�߂Ȃ���........�B
�����A�ԗ��K���╪���M���̘b����o���ƁA���Ԃ���悤�ɁA
�����Əa�������āA��ʎ��̂�������Ƃ������������āA
�����Ԃ��̂т̂ё���ׂ̌�ʋK�����q���ɉ����t����̂́A�~�߂܂��傤�B
�q�����ǂ����Ďq���Ȃ̂��A��l�͔F������ׂ��Ȃ̂ł��B
��ʋK����������w��ł��A�����ɂȂ�ƖY��Ă��܂��̂ł��B
�S�������ɂȂ�Ȃ��悤�ɂƂ����̂ł��傤��
�����ɂȂ�ꏊ���A�����Ǘ����̋����\����A�����قɌ��肵�A
�v���X�e�[�V�����̂悤�ȉ��z�Q�[���ɉ������߂�̂ł��傤���B
���Ȃ�A�ُ�ȎЉ�ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����������ŁA�q���B�͂ǂ̂悤�ȑ�l�ɐ�������̂ł��傤���B
�Ŋ�̌x�@���̌�ʎ��̔����n�}����˂���▾�炩�ł��B
�����Ɋ������H����̌����_�ŁA
��ʋK��������Ă��Ă��q���₨�N���⎩�]�Ԃ��A
��ʎ��̂ɂ����Ă��鎖���ł��B
�������H���ʂ�A���̌����_���A��ʎ��̑����n�тƂȂ�͖̂��炩�ƁA
�x�@���̒S���҂��������Ă���܂��B
���͂�������Ɛ\����Ȃ��̂ŁA�����Ȃǂ͕����ċN���܂����B
���̎Ԃ��ǂ��ł��ʂ������̓��H�Ԃ��čl���A
�ԗ��K���╪���M���≈�������ɂ����S���ĕ�����A
�q���̎��]�Ԃ��ʍs�ł���ܓ��A
�ԗ������グ���Ȃ��A�����݂�K�[�h���[��������A
�ʍs�̕����\���ɂƂ��āA
�d�M����d�M���ɕς��Ă��N������x�݂ł���x���`�ɂ��āA
��ԗp�̃X�y�[�X���m�ۂ����Ԓ��S�ł͂Ȃ����H�Ԃ��A���ɋ}���ł��B
�܂��́A�ʊw�H����ł��B(^_-)��
�������āA���ꂪ�A�������S����n��ɂ����炵�A
���w�Z��n��̃R�~���j�e�B�{�݂��A���ɒn��̒��S�ƂȂ�A
�������S�������������肵���\���̒n��Љ�ƂȂ�A�n�b�s�[�_(^o^)�^
����́A�uBOUNDARY�|���E���\�v�ɂ��Ăł��B
�ǂ����A���y���݂Ɂ`(��o��)�m
�����N�F�@http://www.smilingspace.com
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���̃��[���}�K�W���́A�w�܂��܂��x http://www.mag2.com/ �𗘗p���Ĕ��s
���Ă��܂��B�o�^�E������ http://www.mag2.com/m/0000090643.htm
����ł��܂��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|